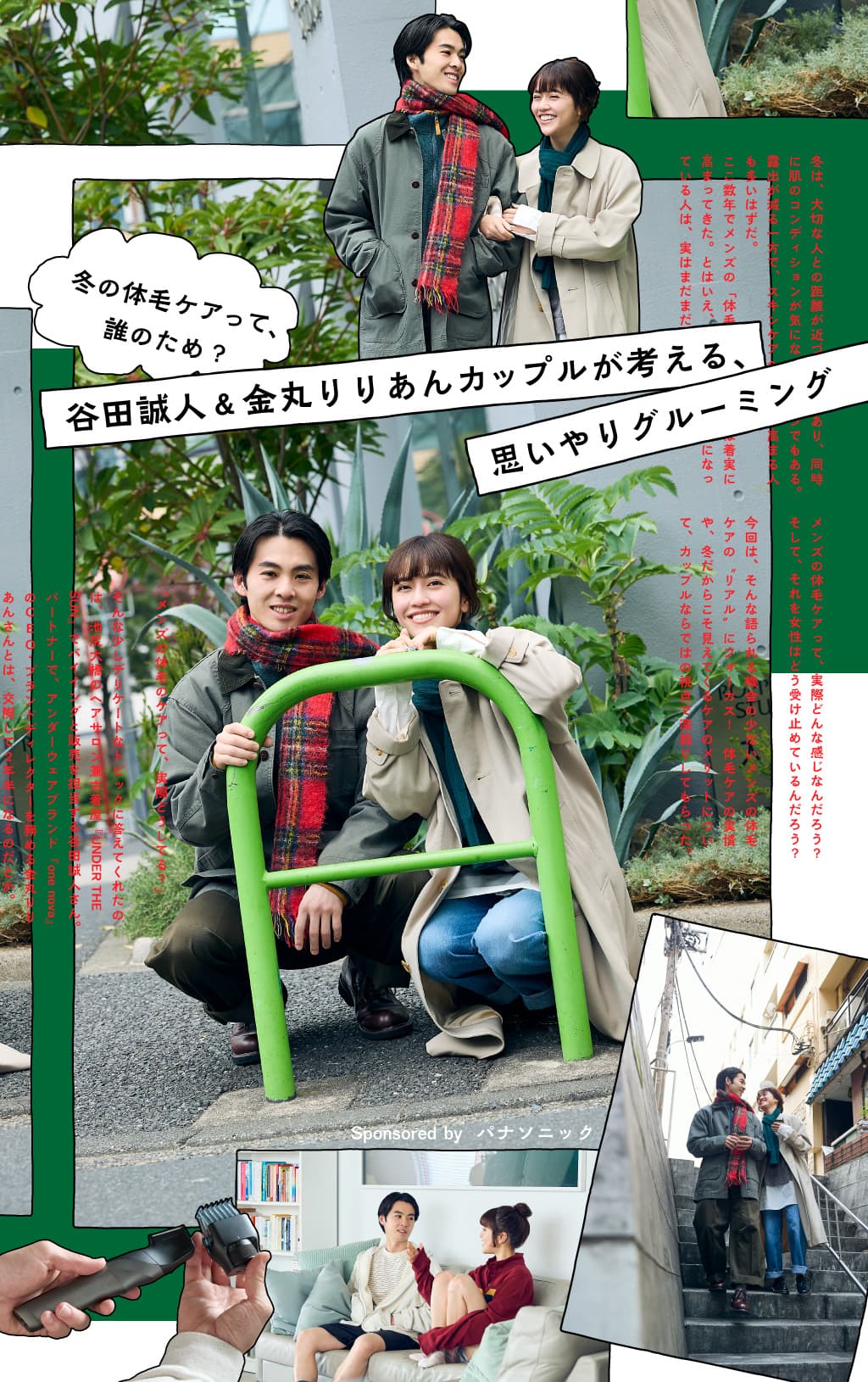私たちの日常生活に、じわじわと浸透してきているAI。創造力を広げたり、業務の効率を上げたり、なにかと便利な存在だけど、「人間の仕事が奪われるかも」「倫理的に大丈夫?」といった不安もまだ拭いきれない。
AIは人間の相棒になるの?それとも脅威になるの?
普段からAIを使っている人たちに、「人間とAIのこれから」について意見を聞いてみよう!
今回のゲストは、クリエイティブディレクターや企画者、映像作家として、多方面で活躍する鈴木健太さん。AIを活用したプロジェクトに携わってきた彼が考える、AIの魅力や課題、そして向き合ううえで大切なスタンスとは?

鈴木健太
映像作家/クリエイティブディレクター
1996年生まれ。10代で映像制作をはじめ、YOASOBI、野田洋次郎、KIRINJIなどのMVや映画、ドラマの監督を務める。多摩美術大学中退後、フリーを経て電通入社。ポカリスエットやHondaなどの広告企画のほか、フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」や、映画レーベル「NOTHING NEW」の創業メンバーを務めた。Google「Geminiと進化中」、Tinder「MATCH FES」、ラフォーレグランバザールなどのクリエイティブディレクションを手がける。文化庁メディア芸術祭優秀賞、映像作家100人選出など。
Instagram:@suzkikenta
X:@suzkikenta
7年前の制作をきっかけに、AIのおもしろさにどハマり!

──まずは、鈴木さんのお仕事について教えてください。
いろいろやっているんですけど、最近は主にふたつですね。
ひとつは、広告の企画やクリエイティブディレクションの延長として、今年「Firstthing」というチームを立ち上げました。ここでは、スタートアップや起業家に伴走しながら、広告に限らずいろんなクリエイティブを手がけています。
もうひとつは、映像ディレクターとしての活動です。小学生の頃に、NHKの番組「デジタル・スタジアム」に自主制作FLASHアニメを出品したときからやっていて、それからも「KIKIFILM」というチームで自主映画を作ったり、最近はミュージックビデオや映画、ドラマの監督や演出を手がけたりしています。

──鈴木さんが、AIに興味をもったきっかけは何だったんですか?
美大を辞めて路頭に迷っていた頃に、「自然言語処理」の研究開発をしている浦川通さんという方とたまたま出会ったんです。そのとき、ちょうどAIのディープラーニング=深層学習が表現の世界で注目され始めていたので、「これを使って、なにかおもしろいことをしよう!」と意気投合して。アイドルグループ「Maison book girl(メゾンブックガール)」の“人間とAIによる音楽の共作プロジェクト”を企画しました。
このプロジェクトでは、プロデューサーのサクライケンタさんがずっと書き溜めてきた膨大な「歌詞」をAIに学習させて、そのAIから生成された新たな「歌詞」をサクライさんがまるで過去の自分と対話するように紡ぎ、「言選り」という曲を作りました。そのプロセスがすごくおもしろくて、そこからAIにさらに興味を持った感じです。
その後も、ANREALAGEというブランドと一緒にAIを用いた衣装を作ったり、「夢」の研究をされている京都大学の神谷之康先生と、人の脳活動情報を学習させた映像作品を作ったりしました。
──当時はAIがまだ発展途上でしたが、最近はどのようにAIを使っていますか?
映像作品では、2023年に公開された日向坂46の正源司陽子さんの個人PVに、AIを用いましたね。RunwayのGEN-1というAIを使ったのですが、当時はまだまだ生成精度が高くなかったので、逆にそれを活かして「インフルエンザの時に見る夢」みたいな世界観を実験的に作らせていただきました。
また同年には、映画レーベル「NOTHING NEW」で制作・プロデュースしたホラーショートフィルム作品集『NN4444』のビジュアルを、AIを独自開発するアーティストの岸裕真くんと一緒に作りました。「不条理」をテーマにした4本の映画本編をAIに学習させて、そこからひとつの顔を生成したんですが、見たことのない一枚の写真が生まれて。ビジュアルは、作品の内容を語りすぎず、見る人の想像を広げるものにしたかったので、世界観を伝えるのにベストな手段となりました。

──ちなみに、仕事以外でAIを使うことはありますか?
Geminiに30分を超えるYouTube動画を要約してもらったり、Higgsfieldという画像生成AIの噂を聞いて試しに使ってみたり。休日に、Figma Makeでポートフォリオサイトを作ったりもしました。
ここ最近は、ManusなどのAIエージェントもすごいですよね。たとえば「この自転車を修理したい」って伝えるだけで、取り扱い説明書を自動で探して読んでくれたり、参考になる動画を開いてくれたり。
Uber Eatsで毎日のお昼ご飯をエージェントに自動で注文してもらってる人もいました。僕は正直、全然使いこなせてないですが、試しに触ってみたりしながら、いろいろリサーチしています。やってみないとわからないので。
AIはクリエイターの「壁打ち相手」になってくれる

──幅広い分野でAIを使われている鈴木さんですが、AIを使うかどうかは、どのような基準で決めているのでしょうか?
個人的に、AIを実験的に用いるプロジェクトって、すごくおもしろいと思うんですけど、この1年くらいで「AIを使うこと」を目的にするのはちょっと違うかなと思い始めています。そのくらい企画や制作には、AIを自然と使うようになりました。
最近の仕事で特に気に入っている使い方は、2024年のラフォーレグランバザールのビジュアルですね。TVVINSというアートディレクターユニットと一緒に、年始のラフォーレ原宿を「早春の大木の幹」と再解釈し「蝶になる前のさなぎ」をコンセプトに作りたいと思ったのですが、撮影できるベストなさなぎを探すのはほぼ不可能で……。最終的にAIでさなぎを作ることを選びました。
この作品もアーティストの岸裕真くんと一緒に作りましたね。あくまで理想のクリエイティブを実現するための手段としてAI を使っています。

──クリエイターがAIを活用するメリットは、どんなところにあると思いますか?
とことん自分に向き合ってくれる「壁打ち相手」になってくれるところですね。クリエイティブな仕事で大事なのって、限られた時間や予算のなかで、どれだけ思考回数を増やし、手を動かして検証を重ねられるかだと思うんです。
自分で何度も試行錯誤するなかで新しい表現が生まれることもあるんですけど、AIを使うことで自分では思いつかない表現や視点と出会えたりします。返ってくる答えが微妙なこともありますけど、それでも粘り強く壁打ちを繰り返していくうちに、自分にとって譲れないこだわりも見えてきたりして。それを言語化できれば、作るべきクリエイティブの軸や像も明確になると思います。

僕の場合、すべてをAIで表現するというよりは、必要に応じて部分部分で使っています。たとえば、自分が考えた企画や作品コンセプトをさらに深ぼったり、登場人物のキャラクター像を書いたファイルをアップして「この人の潜在的な悩みは?」「他の作品だと誰に似てる?」と聞いたり。ゼロからAIと作ることはほとんどなく、自分のアイデアをもとに作品をブラッシュアップするために使うことが多いです。
特にMVは、予算が限られているなかで、いかに魅力的な作品を作れるかが勝負なので、AIによるダイナミックな表現を映像の切り替えに取り入れたり、AIがテストしたカメラワークを実際の撮影に活かしたりしています。
逆に、知り合いの作家さんの中には、「AIに答えを求めるのではなく、自分に向けた“問い”を何個も提案してもらう」とか、「AIに聞いて返ってきた案は普通すぎるからやらない」と決めている方もいて。そういう使い方もおもしろいと思います。
結局、主体性がないとAIの言いなりになるだけで、そうなったら本末転倒ですよね。

──逆に、デメリットは何だと思いますか?
映像を観る側を驚かせるのが、きっとどんどん難しくなっていくことですかね。
昔は、蒸気機関車がスクリーンに向かって進んでくるような描写をスクリーンに投影しただけで、みんなが「わっ」と驚いて逃げるような反応をしていたけど、時代の変化とともに表現の幅が広がって、驚くことは少なくなりました。『ミッション:インポッシブル』でトムクルーズがビルに飛び乗るシーンは、今でも驚きますけどね。
ただ、AIの技術が加速していくと、そういう映像も簡単に作れちゃうじゃないですか。映像技術に対する「驚き」がこれまで以上に薄れて、映像の楽しみ方も変わっていくからこそ、作り手として何をどう表現するかをもっと考えないと……と思います。もしかしたら、映像表現以上にその作品が持つ意味やストーリーが大事になるかもしれません。
「人間 vs AI」よりも「人間 with AI」でいたい

──AIの議論において「仕事が奪われていく」という声も根強いですが、それに対してはどうお考えですか?
これまでの仕事の在り方は変わると思いますし、なくなるものもあると思います。たとえば広告においては、大体のことがクライアントの中で内製できるようになるだろうし、運用も簡単になるだろうし、それに伴って依頼する側の価値観も変わっていくでしょうね。これに関してはもう不可逆な流れなので、変わることを前提に生きた方がいいと思っています。個人的には、新しく仕事そのものを作ったり、AIが普及しても選ばれる人材になったりすることが大事なのかなと。
──どうすれば選ばれる人材になれるのでしょうか?
やっぱり、とりあえず「いてほしい」「話したい」と思われる人は強いですよね。誰にも真似できない才能を持っている、つまり人間力みたいなのが大事になるんじゃないでしょうか。
それから、唯一無二の専門性やオリジナリティを持っている人は、いつまでも選ばれ続けると思います。そういう人がAIを使ったら、もう最強ですよね。
結局、どうプロンプトを打つかというところには創造性が必要で、そこで差が出るんだと思いますね。この人のプロンプトは、この人にしか出せない味がある、みたいな。

最近のAI関連のクリエイティブプロジェクトでおもしろいと思ったのが、エリザ・マクニット監督がGoogle Deep Mindと一緒に制作した短編映画『Ancestra』です。胎児がテーマの作品なんですが、体内にアクセスするシーンがAIで作られていて。AIで制作するところのレンズや光の入り方の設計まで細かく考えているのが印象的でした。
しかも、すべてをAIで作るのではなく、実写映像とうまく合成したり、骨を3Dで作ってからAIに学習させたりと、人間とAIの関係性について考えさせられる内容なのも興味深かったですね。
──専門的なスキルがなくても、AIをうまく活用するには何が大事だと思いますか?
いわゆる「ディレクション思考」みたいなものが重要になってくると思っています。プロンプトって、つまりは何かをディレクションすることで、「どう問いを立てるか」「どう指示するか」がすごく大切なんですよね。
普段からAIを使っていると、プロンプトの書き方がうまくなって、言葉の解像度もどんどん上がっていきます。僕自身、AIに的確に指示するために、これまでなんとなく扱っていた情報を整理して、言語化する習慣ができてきました。
そうやって、ディレクションに必要なスキルが培っていくと、本当はやりたかったことを実現できる人が増えていくと考えていて。起業家が理想のプロダクトを一晩でかたちにできたり、小学生が映画を一人で作ったり、そんなことがもう現実で起き始めている感じがします。
AIが成長すると、人間の仕事が奪われるんじゃないかって思いがちですけど、むしろ人間側が進化するんじゃないかなと。子どもが興味を持っていることをAIに聞きまくったら、AIがいろいろ教えてくれて、その子の夢が見つかるとか。ポジティブな面に目を向けると、未来はめちゃめちゃ明るいんじゃないかなと思っています。

──モラル面でも不安の声が上がっていますが、それについてはどうお考えですか?
最近だと、イラストとか声の無断利用などが話題になっていますよね。これに関しては、AIの会社にも問題があるかもしれないですけど、でもやっぱり使う側の人間次第だなと思っています。
たとえば、マッチングアプリってもともと、普段出会えない人と出会うことを目的とした画期的なプラットフォームなのに、どうしても不純な理由で利用する人っているじゃないですか。ツールが悪いものに見えるのは、相手の気持ちを害するような悪い使い方をしてしまう人がいるからだと思うんです。結局、どう使うかは人間の問題だと思うし、人間そのものがすごく試されている感じがします。
でも技術の最初って、大体そういうものだと思います。YouTubeだって昔は、過去のテレビ番組の無断転載だらけだったけど、そこからルールやシステムが進化して、今では「YouTubeクリエイター」という職業が生まれたわけで。イノベーションの最初に歪みが起きるのは当然で、そればかりを恐れるのは違うかなと思っています。

──最後に、人間とAIがいい関係性を築いていくために、大事だと思う考え方やスタンスがあれば、教えていただけますか?
クリエイターに代わるものというより、「いいものを作りたい」と考えたときに使える手法のひとつとして、AIを捉えるほうがいいのかなと思っています。
ピクサーが生まれたときも、「CGアニメが手描きアニメーターの仕事を奪うんじゃないか」と反発がありましたが、結局は両方残っていますよね。むしろ、手描きアニメーターもコンピューターを活用するようになって、表現の幅が広がったのではと思います。
あくまでもAIはツールでしかないので、人間の代替だと思わない方がいい。「AI vs 人間」と同列に並べるのではなく、「人間 with AI」という関係性で付き合っていく。自分が進化するためのツールとして使うことが大事なんじゃないかなと。「自分の臓器が一個増えた、ラッキー!」くらいに思った方がいいのかなと思います。
鈴木健太が選ぶベストユーズAI
❶「Figma Slides / Figma Make」
プレゼン資料やプロトタイプ作りで大活躍してます。
❷「Runway Aleph」
ついに実用的なAI映像ツールが出てきたなと思いました。
❸「Google NotebookLM」
自分専用の高精度な壁打ちができてすごいです。