プロスポーツ界の最前線で戦うスポーツジムが作った中学野球チームは、はたして令和の“がんばれベアーズ”のような、ドラマティックな結末を迎えることはできるのだろうか? この物語はこれからどちらに転ぶともわからない、現在進行形で進んでいる完全ドキュメントな“野球の未来”にかかわるお話である。野球作家としてお馴染みの村瀬秀信氏が、表に見えるこどもたちのストーリーと、それを裏で支える大人たちの動きや考えを、それぞれ野球の表裏の攻撃守備ように交互に綴っていく。
〜 延長戦 その後の大人たちの物語〜
秋風の中で始まった、静かな回想
夏の熱狂が過ぎ去り、茅ヶ崎の空に秋の風が吹きはじめた頃。あの延長戦を戦った大人たちは、静かに自分たちの物語を振り返っていた。

「あと1イニング。勝たせてあげたかった。負けたのは僕の責任です。本当に総力戦でしたから、ピッチャーがもう残っていなくて。2年生も準備させていたんですけど、最後に責任を取れるのは3年生ですからリョウセイに行ってもらいました。彼は責められません」
あの激戦から1週間後、監督の阪口泰佑は静かに語り始めた。
「勝たせてあげたかった」──監督の胸に残った悔い
「最終回のあの場面。エースのアキヒロを投入することは一切考えていませんでした。確かにその日の朝、本人は行けるようなことは言っていましたし、もしかしたら投げられていたかもしれない。だけど、そんなことをして優勝しても意味がないですからね。僕らの本職はトレーナーです。アキヒロの行動は違和感が発覚した1週間前からずっと見ていました。その上での“投げさせない”という判断です。戦力としては痛手ですが、選手たちには『エースがいなくても、監督がいなかろうが、今いる選手がベストメンバーだ。ひとりひとり、自分ができることをやろう』と伝えました。そして、本当にみんながいっぱいいっぱいまで力を尽くしてくれた。よくやってくれたと言いたいです」
「エースを投げさせない」という覚悟
奇しくも2年前、同じエースだったユウギはひじの痛みのなか、登板を志願して敗れている。その経験は、今回の判断に影響を与えているのだろうか。


「痛みに関してはこちらで最大限のケアをして、最後は本人の判断に任せます。それは1番を背負うエースの特権です。2年前ユウギは“行ける”と言うので投げさせましたが、それはプロのトレーナーとして彼の動きを見て、竹下らと協議した上での判断です。いくら本人が志願しようが、こちらが見て危険だと判断したら投げさせませんよ。ケガの判断に関しては、チームが始まった当初から一貫しています」
決断に対する責任感と自信が強い言葉に表れる。指導者未経験で中学野球の監督になった阪口もまた、このチームで努力を続け成長した人間の一人だ。奇妙な縁である。元々はトレーニングジムに就職したと思いきや、いきなり雑草集団の監督を任せられて、目指すものは全国制覇。1年目は竹下代表にどやされまくり、保護者からも『頼りない。大丈夫かしら』という声が出ていたことも知っている。

雑草集団の監督が成長するまで
チーム設立からここまで、知らないこと、新しいことは積極的に試し、名将と呼ばれた監督たちには頭を下げて教えを乞うてもきた。一方で「若い自分は経験がない分、選手と一緒になって汗を流すことしかできない」と、時に先輩のように、時に兄貴のように選手たちと笑い、怒り、じゃれあいながら、中学生という繊細で、心身ともに大きな成長を遂げる子どもたちの軌跡に目を見張った。
「今のチームのベースになっているものは、1期生が作ってくれたものです。僕らチームスタッフも最初はどうすればいいか正解がないなか手探りだったところに、『こう指導すればいい方向へいく』『これはやってはいけないことだ』と、ひとつの基準を教えてもらえました。彼らは技術も身体も恵まれておらず、最初の頃はまったくと言っていいほど勝てなかった。だけど、自分たちなりにどうして勝てないのか。何が足りないのかを必死に考え、ひとつひとつ努力ながら勝てるようになっていった。そういう話を今の選手たちにもよくするんです。3期生が1年生として入ってきた時に見た、彼らの姿からは想像はできなかったでしょう。その時点ではすでに身体も大きかったし、打つ・投げる・捕る・走る、すべての面で“できる先輩”でしたからね」

1期生が作った「チームの魂」
阪口は「このチームは1期生の成功例があったからこそ」だと言う。野球の技術も力も自信もない無印の子どもたちが、3年間の指導と、子どもたちの努力により成長という結果を残してくれた。野球の上手くない、どちらかといえばヘタクソの集団だった1期生と、無名の指導者はどうして成長することができたのだろうか。
「1期生の何がよかったかって、野球の技術うんぬんの前に、みんなめちゃくちゃ性格がいいやつだったんですよ。素直だし、底抜けに明るいし、ヘタクソな分、上手くなりたいって純粋な思いが強くあった。感心したのが、1年生が入ってきた時に、3年生に威張るやつ、雑用を押し付けるようなやつは、誰もいなかったんです。僕らは何も言わず、ずっと見ていたんですけどね。今の子どもだからなのか、うちが特別なのかはわかりませんが、後輩に対しても仲間の輪の中に入りやすいようにしてあげようという空気を作ってくれた。それがチームとして今も受け継がれていますね」



“いいやつら”が始めた100回の素振り
みんな、いいやつだった。
設立して最初の試合は23-0。市原ポニーを相手に、手も足も出なかった。阪口は試合後「何が足りなかった?」と子どもたちに問い掛け、話し合いをした結果「声を出し、元気では負けない」「1日100回の素振りを続ける」という決め事を作った。
子どもたちは最後まで守り続けた。素直に。本当に、強くなりたい。痛みの思いが生んだ約束を、純粋に続けたのだ。

劇的な変化を生んだのは「積み重ね」
やがて、100キロにも満たないボールしか投げられなかったエースは130キロまで球速を伸ばし、ほとんど野球をやってこなかったセンターは攻守に欠かせないチームの要になった。ボールに当たらなかった4番はホームランのよろこびを知ってしまい、頼りなかったキャプテンは、どこの強豪にも負けない日本一のリーダーシップを突き詰めた。さらには入団時にポヨポヨだった代打の切り札なんて、卒団時には筋肉質の体型に生まれ変わるというビフォーアフターである。


「続ける力」がチームを変えた
劇的に成長する中学生の時期とはいえ、この変化は興味深い。ブラックキャップスは何を教えたのだろうか。
「技術のことは個人個人でありますけど、やっぱり“続けることの大切さ”です。小学生、中学生のクラスでは、最初から身体が大きくてやればできてしまう子供はいます。ただ、壁にぶち当たった時に、『やーめたと』なってしまうことがあるんです。でも、土台からひとつずつ積み重ねてきた子はそうはならない。素振りを一日100回できないんだったら、10回でも1回でもいい。毎日続けること。僕たちが練習を見られるのは週末だけなんです。それ以外の誰にも強制されない平日で、どれだけ積み重ねてこれたか。“自分に負けないこと” そのスイッチが入った選手は、劇的に伸びているし、今できることを“積み重ねる”という1期生が作ってくれたいい伝統が下の代にも受け継がれていったんだと思います」

ラスト・ミーティング──キャプテンが語った“未来”
この秋のベイスターズカップ決勝戦の試合後、最後の円陣で3期生キャプテンのタカヒロが選手たちに向けてこんな言葉を伝えていた。
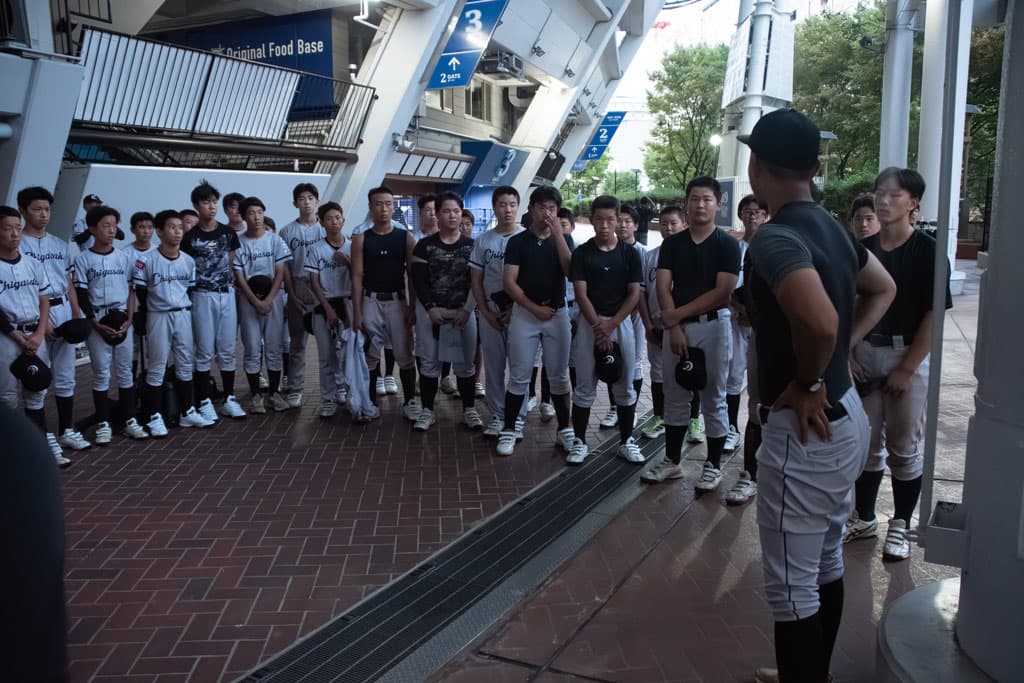

「まだまだ自分たちの野球人生の物語は序章に過ぎないので、積み上げまくって、積み上げまくって、『俺はこんなにやってきたんだぞ』ってプライドや矜持を堂々と表せるように。これから先、それぞれの道に進んでライバルになるかもしれないけど、頑張ろう」
ブラックキャップスを起ち上げた代表の竹下雄真は、タカヒロが発したこの言葉に5年間の実りを感じ取っていた。
「今の時代の子どもたちは、ソーシャルゲームやSNSで簡単にドーパミンが出て、寝っ転がりながらでも手軽に成功体験ができてしまう。ただ、世の中のすべてのこと。どんなに強いチーム、圧倒的な力を持つプロ選手でも、最初からいきなりその場所にいるわけじゃない。本当に身に着くものって、ひとつひとつ努力を積み重ねてはじめて成果が出たものなんです。タカヒロが最後の言葉は、こちらの思いがしっかり伝わっているんだなと、頼もしさを感じましたね」
2020年の冬に「茅ヶ崎にどこにもないチームを作る」と、何もないところからブラックキャップスを起ち上げた竹下もまた、実績など何もない雑草軍団にプロの経験と知識と環境を与える“壮大な実験”を積み上げてきた。
「このブラックキャップスは本当に何もないところからのスタートでした。1期生の最初の頃は、とても戦えるような戦力ではなくても、最後にはベイスターズカップに出場してエリートたちと互角にわたりあえるまでの成果を出してくれた。うれしいのは、彼らたちは強豪校と呼ばれる高校に進み、今でも中心選手として活躍してくれていること。

雑草たちが起こした“ジャイアントキリング”
そして、今年。チームを起ち上げた時に掲げた“ジャイアントキリングを起こす”ということを、3期生がベイスターズカップという大きな大会で、シニアの強豪、中本牧を相手にやってのけたこと。それは偶然でもまぐれでもない。最初から積み上げてきたものが力になって手に入れた勝利です。そこには、スタッフや監督や事務局など裏方たちがチームとして積み上げてきた経験もありますが、核の部分はまったく何もないところから1期生が下地を作ってくれたことです。

彼らは、ベイスターズジュニアから、リトルリーグで全国制覇をした年代トップの選手もいる2・3期生とは違って、本当に何の力もない普通の中学生たちでした。だけど、そんな雑草でも監督コーチの話を聞いて、一生懸命に、正しくトレーニングを積み上げていけば強くなれることを証明してくれた。3期生はその姿を知って、このチームの門を叩いたし、『先輩たちがこれだけ成長できたなら、自分たちはもっと成長できる』と信じて、指導についてきてくれた。いい循環の積み重ねができていた証ですよね」
「やれる」と信じる力が、成長を加速させた
中学生の伸びしろは想像以上に大きなものだ。プロのアスリートを指導してきたトレーナーによる壮大な実験は、いくつもの新たな発見をもたらしたという。
「1期生と3期生の入ってきた時を比べた時、最も大きな違いだったのは技術でも身体能力でもなく、メンタリティです。小学生時代に野球での成功体験がなく、中学では野球を辞めようとしていたぐらいのモチベーションだった1期生に対して、全国制覇や強豪チームのレギュラーなどの成功体験がある3期生は、最初から難題に対して『自分たちがやれないわけがない』と思えるメンタリティがあった。“自分はやれる”と思っている人間は、諦めずに続けることができる。続けられる人間は、今は結果が出なくても、身体ができたり体力が付くことで急激に伸びることが起こるんです。一方で大人にも言えることですが、うまく行かない人、失敗ばかりしている人は、自分に対して自信を持つまでに時間が掛かる。そこに対してどうメンタリティを作ることができるか。これも地道に小さな成功体験からでも積み重ねていくしかないのだろうと思います」
1期生のボロ負けを続ける子どもたちに、成功体験を積ませることは容易ではなかった。負けるたびにどこが悪くて、どうすれば勝てるようになるかを考えさせ、そのためにやるべきことを話し合った。
66日の習慣化。深井諭メンタルトレーナーの講義など、プロのサポートと、少しずつの成功体験で“自分はやれる”というメンタルを積み重ねていく。幸いにもポニーは試合数の多いリーグである。次々と試合をこなすたびに、失敗の中で成功体験と課題は増えていき、2年生の途中から徐々に勝つことが普通のことになっていった。


育成こそが、勝敗を超える価値になる
「勝った負けたも大事だけど、それ以上に大事なことは育成なんですよ。この先、高校・大学と先のステージで野球をやった時、もっといえば野球を辞めて社会に出た時にも、自分に対して自信を持てることがひとつでもふたつでも増えて行けば、それは僕らのやったことに意味があったことになりますからね。
一方で、3期生の一部選手のように、エリート街道を歩いてきた人間の本気をどうやって呼び覚ますかということも僕らはやってきた。これはチームとしての強みですよ。1年勝つだけなら、どんなチームでもいい選手がたまたま集まれば作れる。でも本当に強いチームは、どの代、どの素材が入ってきても安定的に強いチームを作れるんです。これからは“ジャイアントキリングをされる”立場になってくるでしょう。ただ、ブラックキャップスは自分たちのスタイルを崩さずに、カッコよく、常に挑戦していくチームでありたいと思っています」
古い慣習を打ち破り、“中学野球に新しい価値観を”とプロアスリートが行う最先端のトレーニングメソッドと、阪口らコーチ陣による人間の熱が通った指導で、5年間で強豪と肩を並べるまでに成長した茅ヶ崎ブラックキャップス。茅ヶ崎の南口だけからはじまった選手も、今では体験練習会には東京を含む地域から100人以上の参加者が集まる人気クラブになった。

“壮大な実験”は、ひとつの結実を見たと言えるだろう。だが、竹下はこの試みを「あくまでも中学クラブチームの可能性のひとつ」と提言する。
「世の中には、いろんなチームが存在しています。これが全部同じ方針のチームだったらつまらないですよ。いろんな特徴のあるチームがあれば選手には選択肢が増えるし、見ている方も楽しい。世間的には前時代的な指導者が厳しく選手を叱責するチームが叩かれる傾向にあるけど、僕はそれが完全に悪だとは思わない。厳しい環境によってナニクソと反骨心を以て伸びる選手だっているし、逆を言えば、僕らのやってきたことが子どもによっては正しいとも限らないですからね。どの指導や環境がその子どもに合うのか、それは個人個人が見極めて選択していけばいいんです。
自分たちのスタイルを貫くということ
常識は時代や社会によって変わります。チームとして大事なことは自分のスタイルを貫くこと。僕たちは自分たちのやり方が一番カッコいいと思っているし、一番面白いと思っているし、一番正しいことを伝えて、一番成長できるチームだと思っている。僕らは僕らのスタイルを貫く。押し付けることはしません。各チームも自分たちの信じたスタイルを貫けばいい。そうやっていろんなチームがよりよくしようと切磋琢磨して、野球界を、ひいては子どもたちを一人でも多く成長させてあげられる。野球界がそういうものになることを望んでいます」

次の世代へ、バトンは渡された
竹下の視線の先には、グラウンドを走り回る次の世代の子どもたちがいた。
2021年のチーム立ち上げから、1期生14名、2期生1名、3期生14名を送り出し、今もまた茅ヶ崎の文教大学グラウンドでは50名弱の現役選手たちが全国制覇を目指して汗を流す。この先の子どもたちには、一体どんな物語が待っているのだろうか。それはまたいつか、別の話で。
















