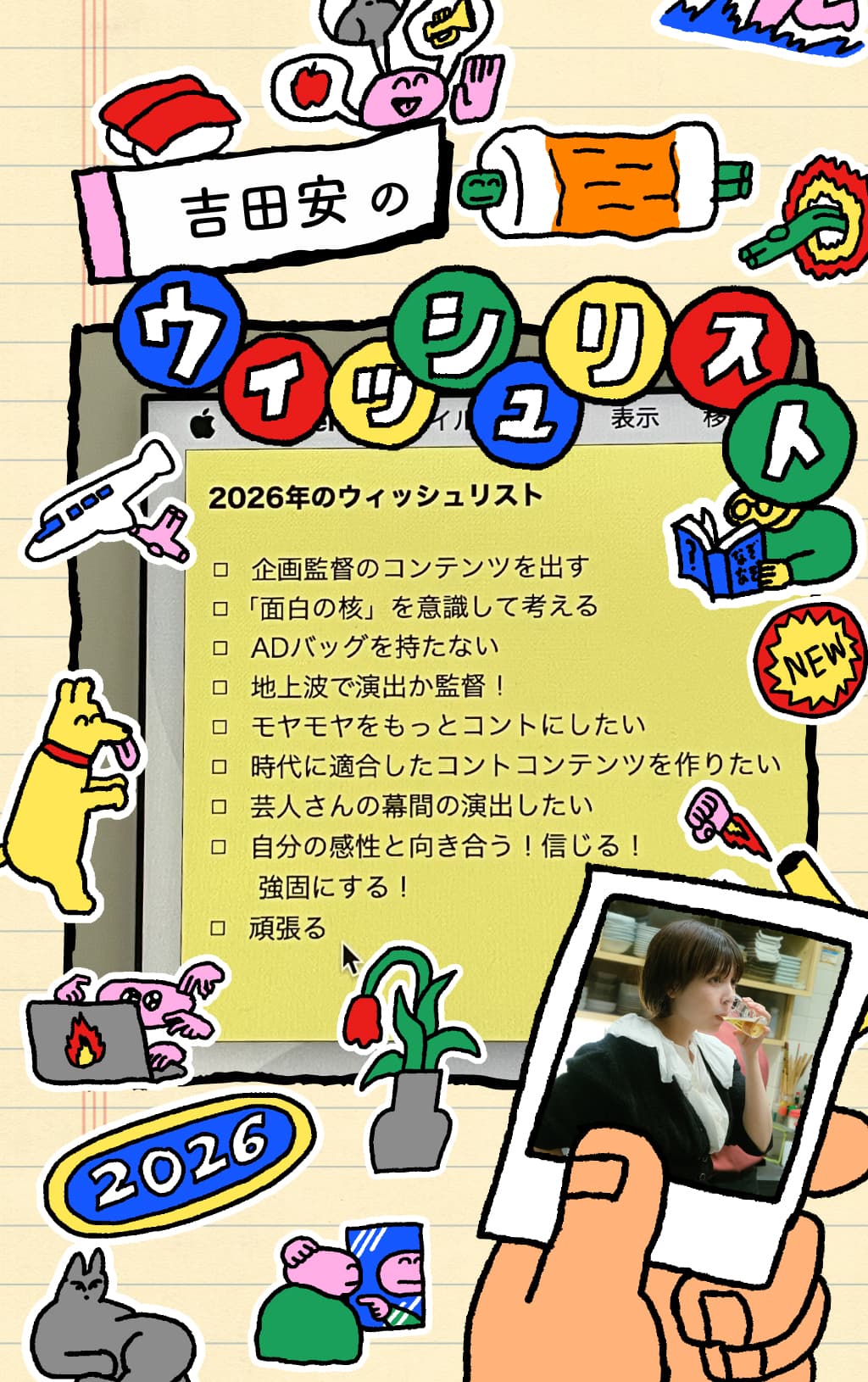心に積もったわだかまりが、見えない爆発とともに消えていく。『ヤングマンベイグ』の佐藤美優さんと小倉巳奈さんは、その瞬間を“モヤモヤボーン“という言葉で表現する。『ヤングマンベイグ』とは直訳で「曖昧な若者たち」。つまり、今を悩める若者の“葛藤”を“爆発”させるための雑誌だ。爆発というと物騒に聞こえるが、その内容はいたってマジメ。誌面では、仕事や結婚、将来の夢など、誰しも一度は抱える悩みを「これでもか」と掘り下げている。

稀人No.003
ヤングマンベイグ・佐藤美優(写真左)/小倉巳奈(写真右)
ともに2000年生まれ、千葉県出身。若者の夢と葛藤をテーマに19歳で『ヤングマンベイグ』を創刊。その他、若者のお悩み相談企画「スナック ヤングマン」などを企画。同世代同士がエンパワーメントできる世の中を目指している。
“鬱憤を晴らすため”につくった雑誌

現在までに刊行された雑誌は3冊。どれも出版取次を通さないため流通には乗らないが、2020年9月に発刊されたvol.1は、都内の店舗数ヶ所から600部が1週間でなくなった。その後、2021年9月にvol.2を、2022年3月にvol.2.5を発刊。今年4月に社会人となったふたりは今、vol.3を構想中だ。
また活動は雑誌づくりにとどまらない。vol.2.5を出版した月には、ラフォーレ原宿「BE AT TOKYO」で雑誌に登場する17人の作品展示・販売を行った。他にも「バー ヤングマンベイグ」と題して都内の飲食店を貸し切り、若者のお悩み相談を受けたり、オフィシャルグッズをつくったり……。
「悩みや葛藤が解消されたときの“ボーン”という爆発が、私と小倉の原動力になっているんです」「そうそう。だから、雑誌を読んでくれた人にも自分の中のモヤモヤを“ボーン!”してもらえたらいいなって」。ふたりは話しながら「私たちの話って擬音が多いんですよね」と笑う。なぜふたりは雑誌をつくることになったのか。

佐藤さんと小倉さんは、ともに2000年生まれのミレニアムベビー。同じ千葉県育ちで、東京の女子大に通いデザインを学んでいた。19歳で雑誌づくりを始めるまで顔を合わせたことがなかったふたりの出会いのきっかけは、2019年9月1日、佐藤さんがSNSに投稿したとある“募集”だ。
「20歳になる前に『2000年生まれの同世代でなにかをつくりたいな』と思ったんです。心の中の“モヤモヤ”をなにかの形で表現したくて。そんなことを勢いでストーリーに流したら、『私も同じこと思ってた!』と小倉からDMをもらいました」
思いがけず届いたラブコール。彼女と会ったことはなかったが、佐藤さんは「この子とならなにかやれそう」だと直感した。集合場所にした渋谷のファミリーレストランで初対面したふたりは、「はじめまして」もそこそこに勢い込んで話しはじめた。
ずっとなにかをしたいと思っていたけれど、なにをすればいいかわからなかったこと。周りの人は好きなことを究めていたけど、自分にはなにもなかったこと。そんな悩みや葛藤を抱えていても、打ち明ける場所がどこにもなかったこと……。
ふたりのモヤモヤが、『ヤングマンベイグ』の原点になった。
大きな丸と、小さな丸

vol.1の刊行にあたって最初に取り組んだのは、2000年生まれがどんな悩みや葛藤を抱えているか調べること。思いつきで、「2000年だから2000人に聞こう」と話がまとまった。しかしオンラインツールを知らなかった当時のふたりは、アンケートを紙に印刷して学園祭で配ったり、友達のツテを頼ったり……。アナログな方法で集めるしかなく、特集6ページの完成におそろしく時間と労力がかかった。学校の勉強とは異なる学びが、そこにはあった。
雑誌のつくり方もイチから学んだ。教えてくれる人なんていないから、アポイントや取材の段取り、Adobeの操作方法から記事入稿の仕方までなんでも調べた。資金づくりのために立ち上げたクラウドファンディングの運用方法もネットで検索した。
そうして初めて世に出した『ヤングマンベイグ』vol.1は、そのユニークさが話題になって600部が1週間でなくなった。フリーペーパーだから利益はなかったが、納得いく物をこの世に送り出せた。愛読する『EA magazine』や『HIGH(er)magazine』の完成度には届かないものの、「“モヤモヤボーン”は達成できたし、これ以上ない結果だ」と感じた。
その達成感が覆されたのは、学生フリーペーパーの祭典「student freepaper forum(SFF)」に参加したときのこと。『ヤングマンベイグ』を置かせてもらった縁で、ファッション誌『装苑』編集長の児島幹規さんと話す機会があった。
そのとき児島さんからされた「丸の大きさ」の話を、佐藤さんは今でも忘れられない。
「君たちが全力を出してつくったと感じている大きな丸は、世間からしたらほんの小さなものでしかない。だけど、君たちならもっと大きく、幅広くできると思う。本当に“葛藤”を表現したいなら、かっこよくしてたらダメだよ」
佐藤さんはその言葉に衝撃を受けた。そして帰り道、すぐ小倉さんに電話した。「私たち、もっとやれることがあるみたい」。こうしてvol.2の製作が始まった。
転換のきっかけになったvol.2

衝動的に走り抜けた『ヤングマンベイグ』vol.1と比べると、vol.2の製作方法はとても堅実だった。製作メンバーを大幅に増やし、部数は600部から1000部に拡大。出版経費を考え、今度は500円で雑誌を販売することにした。
前作と同様、クラウドファンディングで資金を調達すると、『ヤングマンベイグ』チームは完成に向けて動き出した。製作人数が増えた分、予算とスケジュールの管理に振り回されはしたが、ふたりに「苦労している」という感覚はなかった。
特集は、活躍する同世代に向けたインタビュー企画。
その中で、ふたりが「今でも忘れない」と語るのが表現者・アオイヤマダさん。「あの五輪の開会式に出演されていた人ですか?」と聞くと、肯定しながら「正直、苦い経験なんです」という答えが。
「私たち2000年生まれの代表とも言える、憧れの存在のアオイさんが企画書とメッセージに反応してくれて。私たちの活動に共感して、出演していただけることになったんです」
やった、思いが伝わった! と喜んだのも束の間、その熱は急速に萎んでいくことになる。
当日はスタジオを貸し切ったスチール撮影。カメラマン、メイク、照明スタッフをディレクションしながら進行していくのが『ヤングマンベイグ』の役割だった。
「撮影前のインタビューにからしの話があったのを思い出して。〈小さい頃、からしの入った袋を潰して遊んでいた〉というくだりを体で表現してみてほしい、とお願いしたんです。訳がわからないですよね。でも、アオイさんはそのリクエストに『そういうのが欲しかった』と笑顔で返してくれたんです」

ただそんな会話ができたのは、撮影中ほんの少しだけ。あとはアオイさんのパフォーマンスに圧倒され、ふたりはほとんど動くことができなかった。
「想像を超える演技を目の当たりにして、眺めることしかできなかったんです。撮影スタッフへの指示や配慮が足りず、うまく撮影ができなかった。結果的に彼女の魅力を引き出せず、ただの押し付けになってしまいました」
ツー、と冷たい汗が背中に流れた。撮影が進むにつれ、現場の空気は凍っていった。結局、ギクシャクとした雰囲気のまま撮影は終了。インタビューページは完成したが、後悔の残る取材となってしまった。そこからふたりは、『ヤングマンベイグ』のあり方を見直すようになった。
「ふたり」から「みんな」のヤングマンベイグへ

失敗して落ち込むことがあっても、その度に雑誌づくりのための情熱やノウハウを吸収して、そのとき伝えたいことを表現してきた『ヤングマンベイグ』。しかし最新号のvol.2.5は、形も量も少しスケールダウンした。自分たちが本当に知りたいことにフォーカスし、全力を注ごうと決めたのだ。
「vol.1と2の製作を通して、『ヤングマンベイグ』にしかできないことはなにかを考えるようになりました。周囲に目を向けてみると、悩みや葛藤を抱えながらも、好きなことをして輝いている人が大勢いることに気づいたんです。そこで『ヤングマンベイグの読者って、友達や家族のような身近な人の話を聞きたいんじゃないか』とそこで思ったんです」
『スポットライト』と名付けられたvol.2.5は、「人知れず頑張っている人に光を当てたい」という願いのもと製作された。取り上げたのは、アーティストをはじめとする経営者、俳優、活動家など2000年生まれの45人。なかにはギタークラフトマンだったり、ぬいぐるみ作家だったり、ユニークな活動をする人もいる。
前述したようにvol.2.5の発刊月には、ラフォーレ原宿「BE AT TOKYO」で記念イベントが催された。アルバイト先にふたりの活動を知っている人がいて、その紹介で出展させてもらえることになったのだ。
期間中は雑誌の登場者17人の作品が展示・販売され、300人が来場した。目を見張るような成果ではない。しかし来場者と話すうちに発見があった。「人生に悩む若者がまだまだこんなにいるのか」と改めて実感したのだ。
「個人的な感想ですが、イベントは大成功でした。来場者には『同世代に同じ価値観、悩みを持つ人とリアルにつながれることができてうれしい』などと言ってもらえましたし。あの経験から感じたことは、ダイレクトに自分たちの活動を伝えられる場所づくりが、自分たちには向いているのかなということ」という小倉さんは「今後は雑誌という形にとらわれず、“モヤモヤボーン”を表現していきたい」と話す。
不定期で開催しているお悩み相談イベント「バー ヤングマン」は、その代表的な取り組みのひとつ。2000年代生まれの若者が、何に悩み、葛藤しているのか。彼らの抱える“モヤモヤ”に耳を傾け、同世代と語り合った。まさに『ヤングマンベイグ』の実践的な場だった。
「ひとりで参加してくださる方もいます。最初はその場の空気が緊張しているんですが、みんなで話しているうちにあたたまっていくのがわかって好きです。『いつもは聞くばかりで自分の話をしないのに、自然と話してしまった』という感想をもらったこともあります」(小倉)
「驚いたのは、そこが若者同士の出会いの場だけではなく、次のステップを踏み出すきっかけの場になっていたことでした。『将来の夢』をテーマにした回では、農業家と音楽家のヤングマンが仲良くなって、後日、ユニークなイベントを立ち上げていたんです。『スナック ヤングマン』はそういうイノベーションが生まれる空間にもなっているのだなと気づきました」(佐藤)
ふたりがモヤモヤを晴らすためにつくった場所は、いつの間にか“みんなの背中を押す場所”に変わっていた。

新たな“モヤモヤボーン”を求め、おとな1年生に
2023年4月から晴れて社会人デビューしたふたり。どちらも『ヤングマンベイグ』で培った経験を生かせる仕事に進んだようで、生き生きと毎日を過ごしている。社会人になって数カ月、今の気持ちを聞いてみた。
「いい面も、モヤモヤする面も、両方ありますね。幸い自由に仕事をやらせてもらえる会社なので、新入社員としての大変さはありますが、すごく充実していて楽しいです。一方で、プライベートの製作活動になかなか時間を割けなくなったことが一番の悩みです」(小倉)
「そうだよね。それが最新のモヤモヤというか。どうしても仕事が第一優先になってしまって、『ヤングマンベイグ』が疎かになってしまっていることは否めないです。でも、悲観的にはなっていません。これも下積み時代だと捉えればいいかなって」(佐藤)

2020年9月に発刊された『ヤングマンベイグ』vol.1。その表紙には、悩める若者に向けたメッセージが添えられている。
「どこにでもいいから走れヤングマン この世界は全部、きみのものだ」
次号(?)の『ヤングマンベイグ』は、いったいどんな内容になるのだろうか。最新版の“モヤモヤボーン”を見るのが、今から楽しみでしかたがない。

執筆
佐藤稜馬
1992年生まれ、茅ヶ崎市出身。メーカー営業職を経て、2020年からフリーライターに。サーフィン、スケートボード、パルクールなどのアクションスポーツを中心に取材。ライフスタイルや人生観に迫るインタビューが好き。執筆業のほか、地元湘南の海でサーフィンスクールも営む。マイブームは立ち飲み屋にひとりで入ること。

編集、稀人ハンタースクール主催
川内イオ
1979年生まれ。ジャンルを問わず「世界を明るく照らす稀な人」を追う稀人ハンターとして取材、執筆、編集、イベントなどを行う。