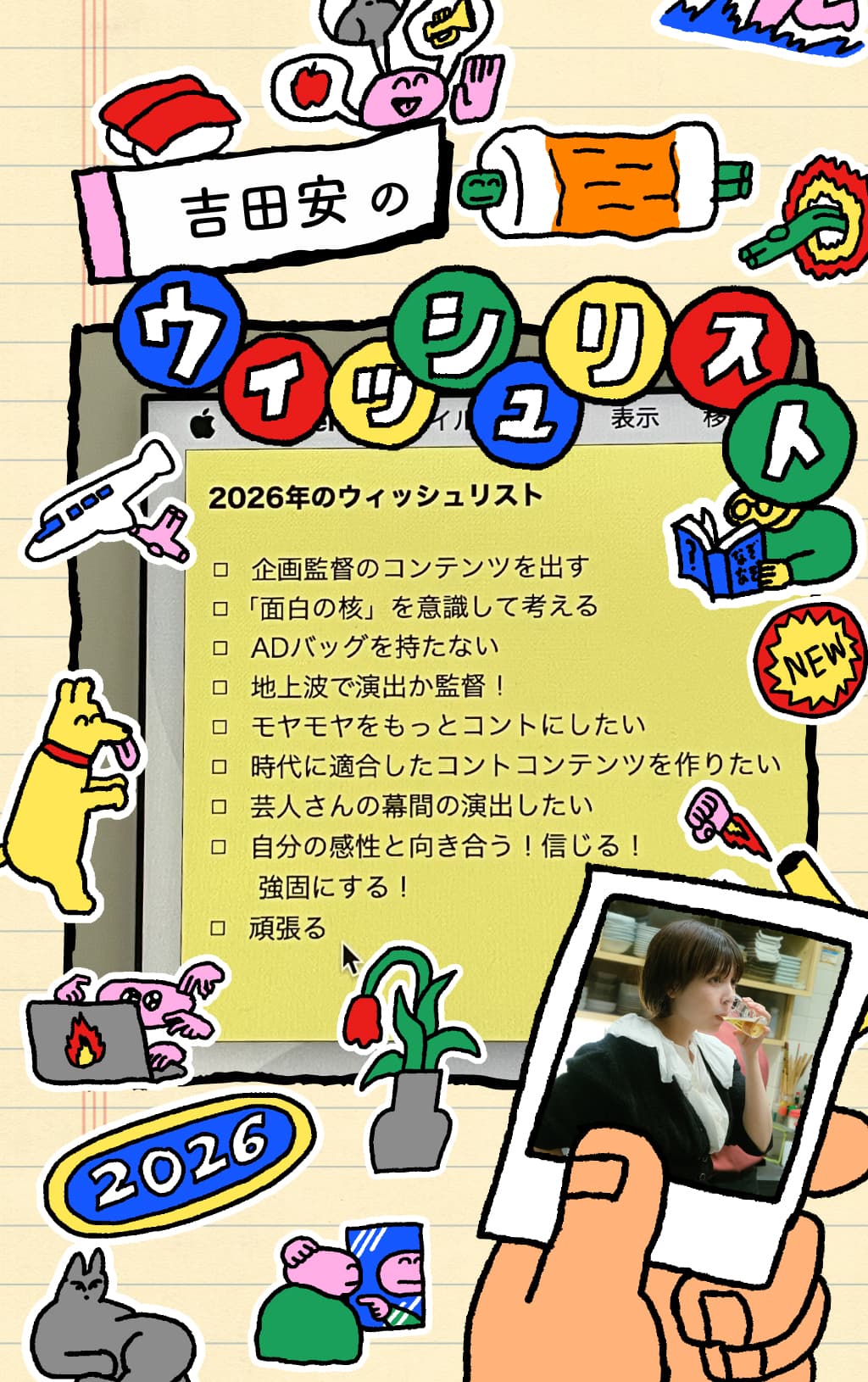Beyond magazine読者のみなさん、こんにちは。ラッパー/詩作家として活動しているmaco maretsです。
冷たい北風に煽られるがまま、街は師走のムード。どこかそわそわするような、あわただしい空気に自然と早足になり、ああ! と気づいた時には段差につまずいたり、時にはそのまますっ転んだり……。なにやら試されているのか、どきどきした毎日を過ごしています。
バタバタ、落ち着かない気分のなかでも見逃してはならない「段差」のごときもの、わたしたちの足元を揺るがすような何かが生活には潜んでいます。その気配をキャッチするためにはきっと、おのれの感覚を目いっぱい研ぎ澄ませておくしかないのでしょう。
今回ご紹介する5つのタイトルは、そうした何か、見慣れた景色を転倒させるものの存在に気づくきっかけをくれるかもしれません。

maco marets
1995年福岡生まれ、現在は東京を拠点に活動するラッパー/詩作家。自身7作目となる最新アルバム『Unready』に至るまでコンスタントに作品リリースを続けている。
Instagram:@bua_macomarets
X:@bua_macomarets
わたし今、ラップ読まされてる? 『ハイパーたいくつ』

松田いりの『ハイパーたいくつ』(河出書房新社, 2024)
第61回文藝賞を受賞した『ハイパーたいくつ』。愛聴しているPodcast番組『奇奇怪怪』で話題になっていたことがきっかけで手に取ったのですが、想像を超えて不条理な展開と、壊れた世界を描く言葉の速度にぐいぐい引き込まれる作品でした。
そんなわけで私はだるだるのスウェットで家から駅までの道を歩いていく。もちろん必要にかられての歩行だから結構ウォー苦。路傍に転がる一本糞はびっくりロン苦。食べたら苦いという意味でby蠅。ワオ。虹がきれい。Eyewear over the rainbow♪ 虹の向こうのメガネ。(本文 p.4)
冒頭からラップの如くリズミカルな口調で綴られる主人公の内面(上に引用したくだりは声に出して読んでみると、より一層おかしみと狂気が増すようで楽しいです)は一見軽快なようでいて、その実! 彼女の見る世界はあちこちがひび割れ、ゆがみ、今にもバラバラになってしまいそうな状態であることがページをめくるうちに分かってきます。
職場でミスを繰り返し、また私生活では浪費癖がたたって借金地獄。写真の帯文にもあるとおり「もう限界」の主人公は、退屈な日々を叩き割らんとひとつの石を放り投げる。そこから物語は読者の目前で加速度的に崩壊していくのです。
終わらない悪夢のような筋書きに、「これは夢や妄想の類であって、主人公が現実に体験したことではないんだ」と言い捨ててしまうこともできるでしょう。しかし、そもそも夢と現実の境目なんてわたしたちが思う以上に曖昧なもの。むしろそんな脆い「現実」への妄執こそが、本作において主人公が壊そうとした「退屈」の正体のようにも思えてきます。
うーん。と私は思った。まことに僭越ながら、どうしてこうまでして人であらねばならぬのか。(本文p.99)
物語終盤、「現実」を踏み越えた主人公は「人であること」を自ら問います。彼女の出した答え、迎える結末は……実際に読んで、確かめてみてください。
息子を亡くした母親の痛切な語り『理由のない場所』

イーユン・リー 著/篠森ゆりこ 訳『理由のない場所』(河出書房新社, 2024)
続いて紹介するのは『理由のない場所』。中国・北京にルーツを持つ米作家、イーユン・リーによって書かれた小説です(邦訳は2020年に単行本として出版されていますが、わたしが今回読んだのは今年・2024年に出た文庫版です)。
語り手の「私」は16歳の息子を自殺で亡くしたひとりの母親。癒えることのない傷を抱えたまま、彼女はこの世にはもういない息子・ニコライを「見つけ」、対話を始めます。それは一見すると生前と変わらない、たとえば夕食の席で交わすような軽口まじりのやり取り。
しかし、ニコライは「私」の現実にはいません。決定的な死によって隔てられた後のふたりは、互いを分かつその境界線の上で静かに言葉を交わしていきます。
今日の天気、あなたはすごく気に入るだろうな、と私は言った。
(中略)
雨なんだね?ニコライが言った。
それに、どんよりしていて寒い。薄暗い。
ぼくが大好きな天気そのものだな。何かお菓子を焼けたらいいのに。
かぼちゃパイなら最高、と私は言った。会話に間を空けたくなかった。焼けたらいいのにという言い方をしたことを、私だけでなく彼も意識しているといけないから。(本文p.65)
実は著者であるイーユン・リー自身も同様に息子を自殺で亡くしており、この『理由のない場所』はその死の数週間後から、「自分の悲しみの本」を作るため、「語り得ぬ悲しみ」を語るために書き始められた、と本書の「訳者あとがき」では述べられています。
そうした背景、作者にとって現実の出来事である死と、作中のそれとをどこまで重ね合わせて良いものか? 正直なところを言えば、わたしには判断がつきません。
ただ、計りしれない悲しみの表現として生まれた『理由のない場所』での対話は、わたしたち自身が経験しうる親しい誰かとの別れ、去来する死への想像を呼び起こすだけの痛切な声に満ちています。
読み終えてしばらくたった今も、ふと背表紙が目に入るだけで胸がざわつくような。忘れがたい余韻を残す一冊です。
70の顔を持つ詩人の代表作が集結『海外詩文庫16 ペソア詩集』

澤田直 訳編『海外詩文庫16 ペソア詩集』(思潮社, 2024 改版)
こちらはポルトガルの詩人、フェルナンド・ペソアの代表作をまとめたアンソロジー。
わたしがペソア作品を読むようになったのは、かれこれ5、6年前、ヨーロッパへの旅行でポルトガルを訪れたことがきっかけでした。なんせペソアは同国で「国民的詩人」として知られており、街中には銅像が立ち、グッズ売り場に顔が並び……と、否が応でもその存在を意識せずにはいられなかった。
実際にその詩を読んでみると、作品の魅力はもちろんのこと、彼が生涯をかけて実践した「異名」というコンセプトに強く惹かれる自分がいました。
「異名」とは、かいつまんで説明すればペソアが創出した「別名義」のようなもの。ただしそれが一介のペンネームに留まらぬ特異性を得た理由は、ペソアが「自分とは異なる人格、外見、来歴、文体をもった、彼自身が<異名>と呼ぶ存在を作り上げた点(本文「解説」p.142)」にあります。
まるきり別の身体と歴史をそなえた人物を生み出し、その「異名者」一人ひとりの手で作品を書いたのです(それもひとりふたりではなく、70人以上の「異名」があったというのだからすごい)。
自身のなかに複数性を認める表現のありようは、言い換えれば唯一絶対の「自分」というフレームからの脱却をも意味します。
わたしの魂は自分を探し
さまよいつづける
願わくは わたしの魂が
自分に出逢いませんように
何ものかであることは牢獄だ
自分であることは 存在しないこと
逃げながら わたしは生きるだろう
より生き生きと ほんとうに
(本文p.10 「(わたしは逃亡者…)」より一部引用)
「ほんとう」の生へと繋がる美しき逃走のかたち。わたしたちは誰もが「何ものか」であることを、自分を自分たらしめる無二の理由を望まずにはいられません。
しかし、ペソアは自ら「異名」というコンセプトを実践しながら「自分」への信仰を切り捨て、「自分であることは 存在しないこと」とまで言ってのけてしまうのです。ね。痺れるでしょう。作品と、その詩の方法とをあわせて何倍も面白く読める作家だと思います。興味を持った方はぜひ。
“観察”ベースのカラッとした家族エッセイ『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』

古賀及子『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』古賀及子(素粒社, 2023)
そのあと娘はさらにフン、とクールな感じのまま「あま紅茶まだある?」と聞いて、あるよ、というと冷蔵庫から取り出して飲んでいた。我が家では「午後の紅茶」を「あま紅茶」と呼んでいる。甘い紅茶だからだ。
人々は家を出た。私は仕事をして、午後は休みをもらって新宿に行き友人に会う。(本文p.34)
『ちょっと踊ったりすぐにかけだす』は、ライター・編集者である著者がWeb上で公開していた日記を書籍化したエッセイ集。
『「学び」がわからなくなったときに読む本』(鳥羽和久 編著/あさま社, 2024)という勉強や子育てをテーマにした対談集に著者が登場しており、そこで語られていた「『感想』を排し『観察』に重きを置く」文章とはどのようなものか知りたくて読みました。これがまたおもしろかった。
じっさい、最初に引用した文中の「人々は家を出た」という一言を拾うだけでもその「観察」的なまなざしが伝わるのではないでしょうか。ぐいとカメラレンズを引いて、母親である自分と、息子、娘の家族3人を「人々」の一言まで抽象化してしまう潔さ。直前の「甘い紅茶だからだ」のくだりを含め、飾らないスパッとした語り口が素敵です。
もちろんすべてが無機質・無感情な情報の羅列というわけではなくて、簡潔な文体のなかにも日々への、子どもたちへの深い愛情が伝わってくる。ただし、過度に家族の生活を賛美することはしない。そのバランス。きっと文章全体の温度を調節するように、絶妙な塩梅で言葉が選ばれているのでしょう。これまで抱いていたウェットで感傷的な「家族エッセイ」ジャンルのイメージを覆すような、さわやかな読後感がありました。
ちなみに今年(2024年)、本書の続編となる『おくれ毛で風を切れ』(古賀及子 著/素粒社, 2024)が刊行されています。こちらもあわせて、おすすめです。
人生が「次のステージ」に移る瞬間『チャック・アンド・ザ・ガール』

サイトウユウスケ『チャック・アンド・ザ・ガール』(TWO VIRGINS, 2024)
最後は恒例の漫画作品を。イラストレーター・サイトウユウスケの手による初のコミック『チャック・アンド・ザ・ガール』は、横浜の街を舞台にした少年少女の成長物語。どこか懐かしさも感じる洒脱な表紙イラストを、本屋で見かけて思わず衝動買いした一冊です。
物語の主人公は「チャック」……ではなく、どちらかといえば「ガール」であるエイミーのほう。アメリカで生まれた彼女は、両親の離婚を期に母のルーツである日本・横浜へと渡り、祖母のテル子と暮らすことに。そこでエイミーは1匹の捨て猫と運命的な出会いを果たします。その猫にエイミーが付けた名前こそがチャックでした。
エイミー、テル子、そしてチャック。ふたりと1匹の横浜での生活は、街で知り合った少年・ケンタ(彼は第2の主人公のような存在です)、テル子の息子・ジョージなど賑やかな闖入者を加えながら続いていきます。しかしどんなに楽しく美しいときも永遠であるはずはなく、エイミーたちはいくつかの別れ、耐えがたい喪失に直面し成長を余儀なくされることになるのです。
若き登場人物の葛藤するさまには、自分が学生のころ抱えていた理由のない不安感、言葉にする術も持たずただただ遊ばせていた、ないまぜの感情たちを垣間見るようでした。また同時にこれから自分が経験するであろう先の苦悩や別離にまで想像が及んでしまい、その痛みのイメージには少々慄く自分もいて。
人生はときどきハードですべてが上手くいかなくなることがある
でもそれはただ次のステージに切り替わる予兆なのかもしれない(本文 p.207)
作中でエイミーが気づいたように、起こる出来事を、それが辛いことでも「次のステージ」への兆しとして受け入れられるかどうか。前を向いて、成長できるかどうか? 自分にはまだ、わかりません。そのときが来たらいつでも読み返せるように、この本を手元に置いておこうと思います。
Text:maco marets
Edit:白鳥菜都