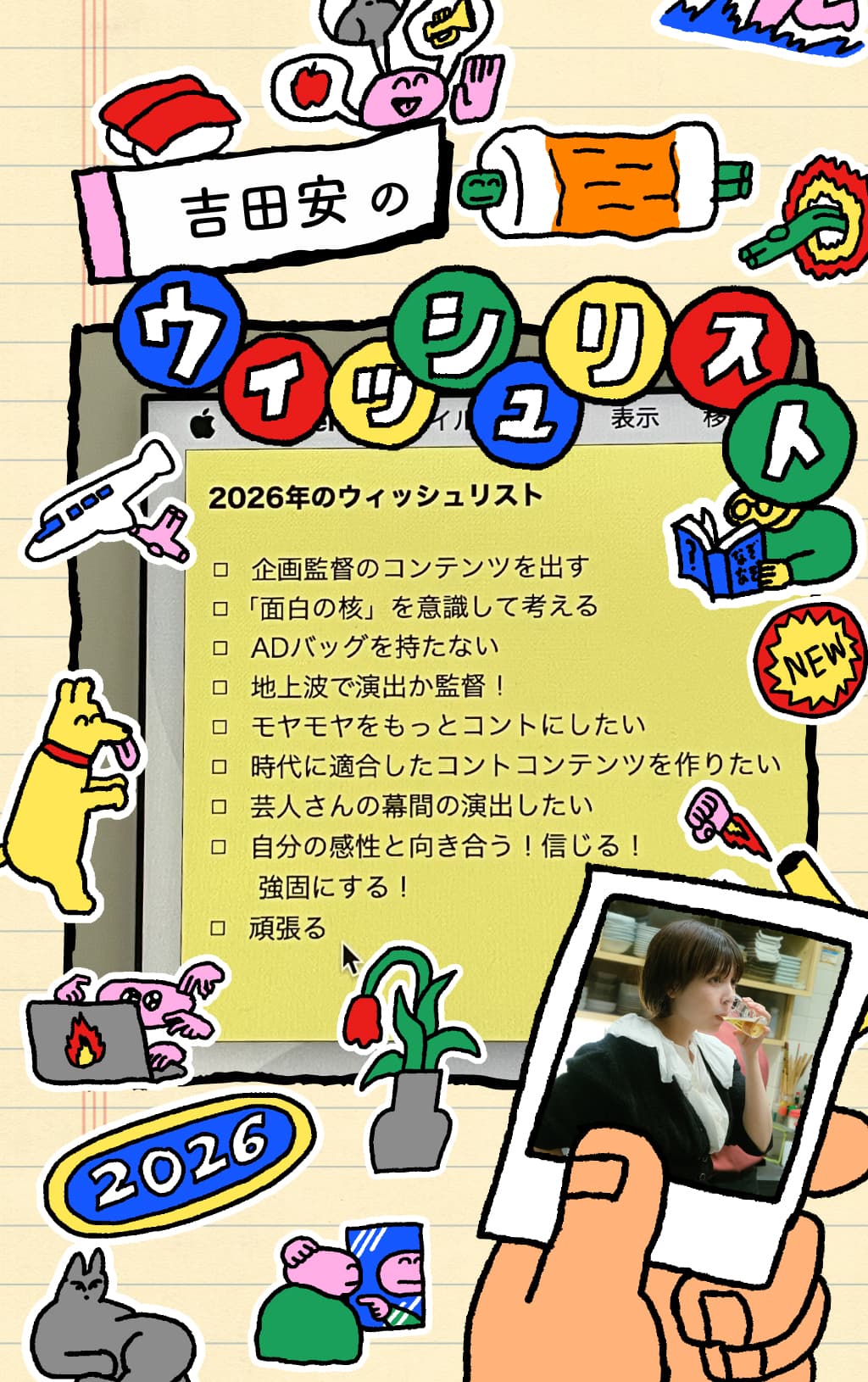Beyond magazine 読者のみなさん、こんにちは。ラッパー/詩作家として活動している maco marets です。
新年の浮き足だった空気もいつしか落ち着き、この原稿を書いている今はちょうど立春のころ。「春のはじまり」とはいえまだまだ寒くって、キーボードを叩く指先もかじかむような、凍える日が続いています。

とくにわたしの作業部屋は木造、かつエアコンも付いていない状態(なぜって、理由は聞かないでくださいね。そういうものなのです)。染み入る冷気に対して、とにかくモコモコに着込んで電気ストーブにしがみつくしかありません。ところがそうすると不思議なもので、今度はなんだか眠くなってくる。気づけばウトウト、机に突っ伏している始末です。
そんなぼんやりとした日々のあわいにも、ハッ! と目の覚めるような瞬間をもたらしてくれたのは……やはり、新しい本との出合いでした。今回も、最近読んだ5つのタイトルをご紹介します。

maco marets
1995年福岡生まれ、現在は東京を拠点に活動するラッパー/詩作家。自身8作目となる最新アルバム『Wild』に至るまでコンスタントに作品リリースを続けている。
Instagram:@bua_macomarets
X:@bua_macomarets
写経したくなる静かな感動『無形』

井戸川射子『無形』(講談社, 2024)
あらすじ
舞台は、立ち退き勧告が進む海辺の団地。年老いて病を患った祖父とその面倒を見る孫娘、夫に先立たれて近所の犬を世話する老女、親が失踪した姉弟など、団地に集う人々の記憶を丁寧に描く。
『この世の喜びよ』で第168回芥川賞を受賞した詩人/小説家の井戸川射子による初の長編小説、『無形』。同じ著者による短編集『共に明るい』や詩集『遠景』は繰り返しノートに書き写すほどの愛読書で、今作の刊行も雑誌「群像」での連載時からずっと心待ちにしていました。
決して大袈裟ではない、むしろ淡々と落ち着いた印象でありながら、いままで感じたことのない言葉の躍動を感じさせてくれる語り口はまさしく唯一無二。特に、登場する子どもたちの描写はその細かな仕草や言動、内面描写のひとつひとつが生き生きと輝くようです。
「磨くというのは、細かな傷をつけていくことなんだと図工の時に何かで見た、記憶でもなんでも磨いていこうではないか、語れば洗練を重ね、人のと繋がり膨らみを増すような、気づきから気づきを得るような。思い出は、四方どこからでも入れる建物だ、崩れるか心もとない、においも飛ぶ、外から光が入り過ぎ見えにくい。」(本文 p.217)
直線では捉えきれない言葉のつらなりに、知らずと読者のまなざしは動揺するでしょう。そこには、硬直した常套句では表しえない、みずみずしい生の手触りが息づいています。
改行がとても少ないのも特徴で、老若男女、登場する複数の人物の視点が次々と移り変わり展開する構成には戸惑う読者もいるかもしれません。しかし、切れ目なく溶け合い連続していくこの文体こそが、「団地」という場に積層する時間、あるいは無数の記憶の集合と言っても良いでしょうか、形のないそれを表現する上で必要な方法だったのだとわたしは感じました。
日々の営みをいかに愛おしむことができるか。人との関わりのなかで、何を喜びとして生きてゆけるか。過ぎゆく時間の暮らし方を問う、静かな感動に満ちた傑作です。
この世を生き延びるお守りに『地球と書いて<ほし>って読むな』

上坂あゆ美『地球と書いて<ほし>って読むな』(文藝春秋, 2024)
「何一つ、私は選んでいないのに。自己決定権がないまま人間をやらされることへの疑問と犯行をずっと心に宿したまま、半ば仕方なく生きてみることにした。」(本文 p.64)
望んだわけでもないのに押し付けられたこの人生。家族という「呪い」。自身を取り巻く「最悪な世界」との、切ってもきれない関係を書いた『地球と書いて<ほし>って読むな』。短歌やラジオ、演劇など、さまざまな領域で活躍する著者ならではの、エネルギッシュな語りにグッと引き込まれるエッセイ集です。
ギャンブルや女遊びに明け暮れ、果ては家族を捨ててフィリピンへと飛んだ父親。ときに知らない人のあばらを折る(⁉︎)ジャイアンのような一面を持つ母。そして「沼津のアリアナ・グランデ」なる異名を持つ、自由放埒な姉。「ふつう」でない家庭環境に生まれ、周囲とのギャップ、決して自分の思うようにはならない不条理に振り回されてきた日々。
これまでの人生を回顧しながら語られるエピソードはどれも強烈で、おかしくて、でもどこかズキズキと痛むよう。他人と関わり合いながら、少しずつこの世界で「生き延びる方法」を手にしていった、その闘いの記憶が生傷だらけの言葉で綴られています。
印象的なのが、エッセイの合間に挿入される短歌の存在。それはきっと、著者自身が見出した世界の「真実」、その凝縮です。たった1行、31音に刻まれるエモーションの、なんと痛烈なことか。
生きること、そのままならなさに頑として立ち向かう著者の言葉には、同様の苦しみを感じたことのある人なら誰もが大きなパワーをもらえるはずです。また1冊、お守りとして手元に置いておきたい本が増えました。
「なんとなくヤバそう」を紐解く『アメリカの未解決問題』

竹田ダニエル/三牧聖子『アメリカの未解決問題』(集英社, 2025)
2025年始、日々のニュースを騒がせている大きなトピックのひとつといえば間違いなくアメリカのドナルド·トランプ大統領の動向でしょう。就任後、数々の方針転換によって世界情勢が大きく動こうとしている。
その「なんとなくヤバそう」なムードは感じていても、この状況がどうして生まれたのか、今、アメリカ本国で何が起きているのか、実際のところを知るのは容易ではありません。わたし自身もそうですが、何をとっかかりとしてこの問題を考えてゆけばいいのだろうと、迷う方も多いのではないでしょうか。そんな人におすすめしたいのがこの『アメリカの未解決問題』です。
本書はZ世代のジャーナリストとしてアメリカの価値観を日本に紹介し続けているほか、エージェントの立場で音楽業界にも関わるなど幅広く活躍する竹田ダニエル、そして米国政治外交史を専門とする研究者·三牧聖子の両氏による対談本。大統領選の詳細、パレスチナ問題への関わり、若者とSNSのトレンドまで、アメリカの今を知る足掛かりとなるポイントが語られています。
読んでいくと分かりますが、ドナルド·トランプの勝利という形で顕在化したアメリカ社会のジレンマは、日ごろニュースメディアなどで流し見している印象以上に深刻です。「ハリスフィーバー」の盛り上がりを呑気に支持していた自分の、認識の甘さを痛感せずにはいられませんでした。
大国の「未解決問題」は日本で暮らすわたしたちにとっても決して他人事ではありません。貧困、差別、戦争。「世界で起きていることすべてがつながっていて、個人の力ではなかなか変えられないことがわかってきてしまった」絶望の時代にあって、それでも生きていくために。今起きていることを知り、考えるきっかけをくれる1冊です。
あなたはなぜ本を集める?『本なら売るほど(1)』

児島青『本なら売るほど(1)』(KADOKAWA, 2025)
あらすじ
脱サラした青年が営む古本屋「十月堂」。気だるげな店主の元に、高校生から老人までさまざまなお客さんが訪れる。1話完結型のクセありなお客さんの本を巡る物語。実在する書籍が登場する点にも注目。
以前この連載で紹介した『百木田家の古書暮らし』や、小説『森崎書店の日々』『ビブリア古書堂の事件手帖』など、いわゆる「古書店もの」はひとつの人気ジャンルと言ってもいいかもしれません。ラブコメだったり、ミステリーだったり、さまざまなシリーズがありますよね。
今回紹介する『本なら売るほど』は、若き店主が営む古書店·十月堂と、その場所を訪れるさまざまな人々を描いたコミック作品。人と本との関係に焦点をあてた、新たな角度の「古書店もの」です。
ここではネタバレにならないように書きますが、作中では、「自身の蔵書を全く読んだことのない人」や、「自分の『作品』のために大量の本を買い集めていた人」など、読む人によっては「それはちょっとどうなのよ!」とツッコミたくなるであろう人物が登場します。
もちろん、彼らが本を手に取る理由だって決して「間違い」とは言えません。誰もが言葉や物語に感動したがっているとは限らないし、書かれている内容は問題でなく、ただ本という「モノ」の存在が必要とされる場合もある。こうした本の捉え方がとてもリアルで、誠実だと感じました。
結局、本に対する価値観は人によってさまざまで、だからこそ、それを介して行われるコミュニケーションも一筋縄ではいかないということ。作中描かれるように、ポジティブな対話のきっかけにもなれば、すれ違いや衝突を生む結果にもなりえるわけで……。善い悪いではなく、それだけ開かれた可能性を有しているのが本という存在なのでしょう。
人と本との関わりあい、その豊かさ・多様さを教えてくれる『本なら売るほど』。この先、本をめぐってどんな物語が描かれていくのか。続刊の展開が楽しみです。
たまには蛙語の絵本でも『声にだすことばえほんごびらっふの独白』

草野心平 詩/いちかわなつこ 絵/齋藤孝 編『声にだすことばえほん ごびらっふの独白』(ほるぷ出版, 2007)
最後に紹介するのは、詩人·草野心平による代表的な詩作品『ごびらっふの独白』を絵本化した1冊。もともと荒川洋治·著『ぼくの文章読本』で紹介されていたのを読んで興味を持ったのですが、実際触れてみるとこれがとても良かった。
なんといっても、この作品の大きな特徴は本文がすべて「蛙語」で書かれている点です。えっ、どういうこと、と思う方もいるでしょう。蛙の言葉なんてあるのか、ゲロゲロ、クワックワッ、みたいなことか。ここで『ごびらっふの独白』の冒頭を引用してみます。
「るてえる びる もれとりり がいく。
ぐうであとびん むはありんく るてえる。」(本文 p.4-6)
いかがでしょう? 何を言ってるかサッパリですね。でもなんとなく、小さな蛙が独り言を言っているさまを想像できませんか。「るてえる びる」の「る、る」と続く感じも、あの長いベロで巻き舌っぽく喋っているのかな、なんて想像したり。「ぐう であとびん」なんて声に出して読んでいると、なんだか愉快な気持ちになってきます。
こうして架空の「蛙語」を味わうだけでじゅうぶん楽しい作品だけれど、「意味を知りたい」という人のためになんと「日本語訳」も用意されているのがこの詩の親切なところ。先ほど引用した部分を人間の言葉に直してみると、こうなります。
「幸福といふものはたわいなくつていいものだ。
おれはいま土のなかの靄のやうな幸福につつまれてゐる。」(本文 p.30)
実はこの蛙は「幸せとはなにか」について思いをめぐらせているところなのでした。まさかこんなことを喋っていたのか、とびっくりしますよね。この「日本語訳」の内容がまた素晴らしく、何度読んでも飽きません(詳しくは本文を読んでもらいたいところ……)!
自身の孤独と幸福とを静かに見つめ、今この生命を愛おしむことを教えてくれる「ごびらっふ」のひとりごと。そのおおらかな声は、日々の生活に疲れを感じている人にこそ優しく、強く響くものだと思います。気になった方はぜひ、読んでみてください。
Text:maco marets
Edit:白鳥菜都